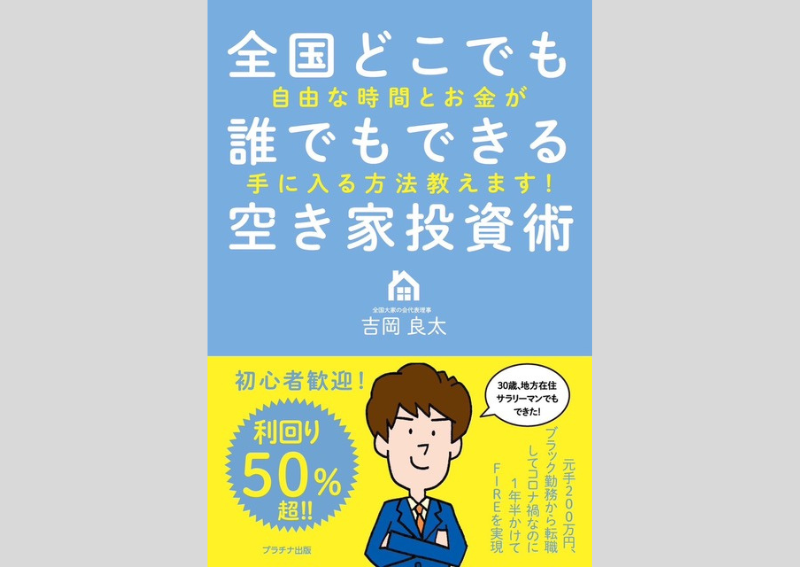「生産緑地 2022年問題」にどう向き合うか

2018/06/08

農地の宅地化が進められてきた歴史

フジ総合グループ代表 藤宮 浩氏
日本経済におけるインバウンドの効果は大きく、地価もご多分にもれず訪日外国人客でにぎわう地域での上昇が目立っている。実際、国税庁が7月3日に発表した2017年分の路線価(1月1日時点)によれば、東京都は前年比3.2%の上昇と、16年の上昇率2.9%を上回った。その一方で、不動産投資家を対象に野村不動産アーバンネットが行った調査では、「今、投資用不動産は買い時だと思いますか」との質問に「買い時はしばらく来ないと思う」という答えが52.2%と、09年の調査開始以来、初めて半数を超え、地価高騰への警戒感も出ている。
都市部の地価は依然として上昇基調にありながらも、不動産市場に対する漠然とした不安があることがうかがえる。そして、こうした不安を一層高めているのが、現実の問題として姿を見せ始めている「生産緑地 2022年問題」である。
生産緑地制度とは、生産緑地法に基づき、3大都市圏特定市を中心とする各自治体が、市街化区域内の一定の要件を満たす農地を「生産緑地地区」として指定する制度のこと。生産緑地に指定されると、固定資産税等の軽減、相続税の評価減、相続税の納税猶予といった税金の優遇措置が受けられる。指定を受けるには、その農地が良好な生活環境の確保に効果があり、公共施設などの敷地に適していること、原則500㎡以上の面積であること、農林業の継続が可能な条件を備えていること、などの条件がある。
このように税制面でのメリットを受けられるものの、土地そのものの用途は農林業に固定されるため、建物の建築などに制限が課される。一度指定されると、一部の例外規定を除いて「売れない」「貸せない」「建てられない」「(農林業を)やめられない」状態になってしまうという側面があるのだ。
「生産緑地は良好な都市環境を確保するため、都市部に残っている農地を計画的に保全することを目的としています。その一方で、今の生産緑地制度が開始された1992年はバブル末期で地価が高騰しており、住宅供給の必要性から、宅地化すべき農地は課税を強化し転用を促進するというねらいもありました」
こう話すのは、相続・不動産コンサルティングを手がけるフジ総合グループの代表で不動産鑑定士の藤宮浩さんだ。都市部の農地はこれまでも日本経済の動きと密接に関係してきた。
その歴史は1969年の「都市計画法」の施行からはじまった。この法律によって、「市街化区域」「市街化調整区域」の区域区分制度が創設。そのうえで市街化区域内の農地は“宅地化すべきもの”と位置づけられた。以降、当時の住宅需要の高まりを背景として、行政は宅地並みの高い税金をかけることで都市農地の利用転換を図っていくが、一方で農地所有者や農業団体等の反対も根強く、農地保全と宅地化促進の調整の必要性から様々な制度の変遷を辿ることとなる。
74年には「生産緑地法」が制定され、市街化区域内農地に生産緑地地区が指定されることとなった。当時の生産緑地はその機能により第1種及び第2種に区分され、買取申出ができるまでの期間は第1種が10年、第2種が5年、指定面積の基準は第1種がおおむね1ヘクタール以上、第2種がおおむね0.2ヘクタール以上とされた。
82年には「長期営農継続農地制度」が導入された。この制度は、長期営農継続農地の認定を受けた農地について固定資産税等の宅地並み課税を猶予し、5年間営農を継続した場合にはこれを免除するというものだ。
そして、91年にいわゆる「新生産緑地法」(現行の生産緑地法)が施行。この改正により、市街化区域内農地は「保全すべき農地」と「宅地化すべき農地」に明確に線引きされた。生産緑地の第1種・第2種の区別は廃止され、その指定面積要件は500㎡、買取申出ができるまでの期間は指定後30年と設定。政府は都市農地所有者に対して、30年の営農継続と引き換えに生産緑地の指定を受けるか、利用転換できる代わりに宅地並み課税を受け入れるかの選択を迫ったのである。
15年3月末の国土交通省の資料によると、生産緑地の指定を受けている地区は全国で62,473地区、面積にすると13,442ヘクタールに上り、このうちのおよそ8割が1992年の制度開始時に指定を受けている。したがって2022年がその30年目にあたり、市町村への買取申出が急増することが予想される。実際は財政上の問題から買い取りに応じる市町村は少ないと見られ、解除された生産緑地の多くが宅地として不動産市場に売りに出される結果、供給過剰で地価が暴落するのではというのが、「生産緑地 2022年問題」なのである。周辺の宅地化が進めば既存の賃貸住宅の家賃に影響を及ぼすことになりかねない。しかも22年は東京五輪を終えた2年後で、五輪景気もおわって景気が踊り場になっていることも危惧され、そこに地価の下落が相まって不況に拍車がかかるのではないかと危機感が高まっている。
地価、賃料に与えるインパクト

現実的にはどのくらいの生産緑地が不動産市場に流入するのだろうか。藤宮さんは次のように話す。
「相続税の納税猶予の適用を受けている人は、東京都では5割程度いると見られます。これらの方は、生産緑地を解除するとさかのぼって相続税と利子税を納めなくてはならないので、現実的には動きたくても動けない状態だと思います。加えて、先祖代々の土地だからやはり売りたくないという人や、要件緩和などの影響で解除を踏みとどまる人が3割程度いると考えると、流動的な生産緑地は残りの2割程度ではないかと見ています」
生産緑地全体のおよそ25%は東京都に集中しており、東京の地価に最も大きな影響が及ぶことが予想されている。そのため土地、賃貸マンション、アパートオーナーとしては、この動向を注視しておくことが重要だ。
「東京都心部は需要があるので、土地を売る側としてはまだ有利だとは思います。一方で、郊外など周辺の需要が奪われる可能性があり、とくに郊外のベッドタウンなどでは地価の下落や空き家の増加が深刻な問題になるのでないでしょうか。都心を中心に、ドーナツ状に外に行くほどその傾向が強まると思います」
と話す藤宮さん。さらに、賃貸マンション、アパートオーナーが気をつけるべき点を、こう指摘する。「これからアパートやマンションを建てるならば、周辺の生産緑地の状況を把握しておく必要があります。生産緑地が戸建用地や賃貸・分譲マンション用地として活用されれば、近隣に競合物件が増え、賃料や空室率に影響が出ると考えられます。そういったことも想定したうえで賃貸経営をしていかないと、空室が埋まらないという状況にもなりかねません」
表は、1都3県にある生産緑地が多い市町村ランキングだ。23区では練馬区は8位、世田谷区も33位と生産緑地が多い。また、人気の吉祥寺のある武蔵野市は72位だが、14位の三鷹市、22位の西東京市、58位の杉並区、上述の練馬区、世田谷区に囲まれているため、安心はできない。このように、隣接地域も含めて俯瞰して見ることも必要だ。

政策を180度転換
生産緑地はこうした大きな影響が出そうな問題だけに政府も見過ごしてはおらず、農地保全のための対応策を打ち出してはいる。
まず、15年4月に施行された「都市農業振興基本法」と、それに基づき定められた「都市農業振興基本計画」である。この法律の整備と計画の策定は、食への安全意識の高まり、人口減少に伴う宅地転用の需要低下、都市の景観や環境保全、農業への理解の浸透、防災空間としての農地活用といった社会状況の変化を受けたもの。都市農地の位置づけをこれまでの「宅地化するもの」から「都市にあるべきもの」へと方針転換した。都市農地の賃貸や税制優遇措置の継続なども検討されている。
さらに、17年6月には生産緑地法の一部改正を含む「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行された。
その骨子の1つとして、これまで生産緑地指定を受けるには面積が500㎡以上必要だったところ、市区町村がそれぞれの条例で300㎡を下限に引き下げることを可能とした。2つ目として、これまで建築が認められていた一定の農業関連施設に加え、ジャム等の製造・加工所、直売所、農家レストランなどの建築ができるようになった。3つ目としては「特定生産緑地」の新設が挙げられる。これまでは指定後30年を経過しなければ生産緑地の買取申出ができなかったが、特定生産緑地に指定されれば10年経過後に買取申出できるようになる。また、10年経過時に再度指定を受けることもできるという柔軟性を持たせた。
しかし、こうした施策だけでは不十分だと藤宮さんは話す。「生産緑地の面積要件や建築制限の緩和、特定生産緑地の創設などにより生産緑地の継続を選択しやすくなりましたが、正直、このような施策では生産緑地の宅地化は食い止められないと思います。もう少し抜本的な案が必要です」
そのうえで自らできる対応策も検討しておく必要があるという。
「生産緑地自体は自由に解除できるものではありませんが、生産緑地以外で資産価値の向上が見込めない土地を持っているならば、市況のいいうちに売却するという選択肢もあります。ただし、土地を売った代金をそのまま現金で保有してしまうと相続税の負担が大きくなりますので、利回りのよい不動産などに資産を組み替えるのも1つの方法でしょうね。
また、生産緑地は30年が経過する以外にも、主たる農業従事者が亡くなった場合や、一定の病気やけがで農業に従事できない事由がある場合にも解除できます。仮にこうした条件にあてはまっているならば、22年を待たずに解除して売却した方がいい可能性もあります。実際に私が携わった事例では、農業に従事している方が高齢で長期入院しているなどの事情があったため生産緑地を解除し、都心の区分マンションなどに資産の組み替えを行いました」とはいえ、親族などのしがらみもあって、なかなか売れないという人も多い。
「いずれにせよ、まずは自分の資産状況や問題点を把握することが大切です。農業が継続できるのか、解除後の固定資産税を払えるのか、宅地化した場合に収益性のある事業に活用できるのか、あるいはいくらで売却できるのかといったことをシミュレーションしておけば、生産緑地の継続判断や将来の相続に備える手立てになります」
2022年まであと4年、選択のタイムリミットは近づいている。
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。